9月29日、フリーホラーゲーム「アクアリウムは踊らない」はサンシャイン水族館(東京・池袋)とのコラボイベント『サンシャイン水族館×アクアリウムは踊らない 体験型ホラー水族館 「アクアリウムは目覚めない」』の開催を決定したと発表。開催日時は10月10日(金)~11月3日(月・祝)の各日18:15~21:00、料金は大人(高校生以上)2,600円~3,000円、こども(小・中学生)1,300円、幼児(4才以上)800円。本イベントは通常営業時のチケットでは入場出来ないため、別途チケット購入が必要である。
館内BGMや特別装飾で“癒し”の水族館が一転し、“恐怖・不気味”な空間へと様変わりする。 「アクアリウムは踊らない」の世界観を再現した夜の水族館の中で、参加者全員が主人公となって物語を楽しめる謎解きラリーを実施するとの事である。謎解きラリーは前期・後期と分かれて実施され、それぞれ異なるエンドカードが提供される。公式グッズの販売も先行して行われるとの情報もあり、ファンにはたまらない一時となりそうだ。
アクアリウムは踊らないという作品について

同作はRPGツクールにて制作された無料作品、いわゆるフリーゲームの一つである。作者である橙々氏は8年間を費やし同作を開発・完成させている。2024年2月のリリースからわずか2日間で10万DLを達成し、その後もプレイ実況やSNSでの口コミを受け70万DLを突破。先日の東京ゲームショウ2025でも作者がステージに出演を果たすなど、様々なメディア展開もあわせてかなりの勢いで広がりを見せている。
同作はアクアリウムという名が付いている通り、水族館が舞台のホラーRPGだ。「ビアンカ水族館」を訪れた少女・スーズと親友のルルが館長の妻の手引きで水族館を見学していたが、ルルの姿が見えなくなったのでスーズは水族館を探し始める。その刹那、水族館が見たこともない空間へと様変わりし、水棲生物が襲いかかる恐怖の水族館へと変貌。親友を無事に見つけ出し、水族館を脱出する事が作品の目標となっている。
作品を通してジャンプスケアとなる要素が少なく、総じて「遊びやすい」ホラーゲームの入門編としてオススメしやすいタイトルである。少々変わり種ではあるが、同作は最速でエンディングを人力操作にて目指す「RTA(RealTimeAttack)」のタイトルとしても取り上げられた経緯がある。作品のバグを最大限活用してのプレイということで、作者も認知した上で同タイムアタックがRTAinJapan内で行われた。作者からは「公開処刑」との悲鳴もあがっていたが、バグ要素を活かしたプレイの様子にファンアートが生まれたりするなど概ね好評でイベントが終了したため稀有な事例と言えるだろう。
様々な方向で話題となっている同作をはじめ、RPGツクール発のゲームだからといってどれもこれもチープさの残る作品とは限らない。この手のタイトルの金字塔として語られる作品の一つは、2004年にリリースされ、2007年にバージョン0.10が公開された「ゆめにっき」だ。
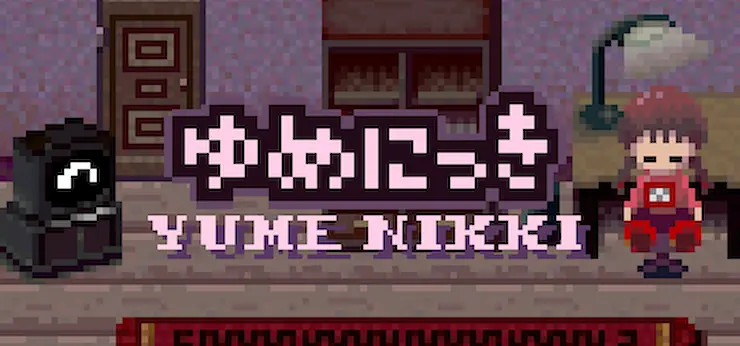
RPGツクールという土台から芽吹いた夢
同作はRPGツクール2003を使用し製作されている。現在で言うジャンルではウォーキングシミュレーターに分類されるタイトルであり、広大な夢の中をあてど無く歩き、様々な「エフェクト」を手に入れ、夢の中に影響を及ぼしたりフィーリングだけの要素であったりを駆使しながら放浪するゲームとなっている。ゲーム内には一応明確な目的はある上に、作者としては「アドベンチャーゲームサバイバルホラー」という体であるのか種々雑多な要素が存在しながらも、見る人によってはメッセージ性を感じるものが多く散見される。また現代で言う所の「リミナルスペース探索系」に近しいものであるとも形容できるだろう。
作品は発表直後から口コミでじわじわとDL数が増えていき、Vectorの2009年度年間総合ランキングでは68位にランクイン。20周年記念イベント「Vector Award」においては、ダウンロードソフト約10万本中14位にランクインしている。同サイトの上位にはブラウザや業務で役に立つフリーソフトなどが軒を連ねている中でのゲーム作品のランクインというのは珍しいケースである。その後もオフィシャルTシャツやぬいぐるみ、アクリルキーホルダーが製作されたり、同人作品としての二次創作タイトルや関連ソフトウェアである「YUMENIKKI -DREAM DIARY-」の発売が行われたりしている。
とはいえ同作品の作者であるききやま氏は、作品発表は行っているが殆ど外界とのコンタクトを取っておらず、ごく一部の人物が限定的に同氏へのインタビューや対談を行い、一部の関連ソフトウェアには監修を行っているという情報のみが伝わる謎深い人物でもある。未だに人気のある同作に対して氏が表に出てこない点は、昨今制作者が前面に押し出されていく風潮が強い中で未だに興味深い要素の一つと言えるだろう。
RPGツクールといえば確かに様々な作品があるだろうが、それでもこういった「当たれば芽吹く」作品は存在する。いかにこういった作品を作り、世に出していくことが出来るのか。作る側も見出す側も、慎重な審美眼が試されている。

